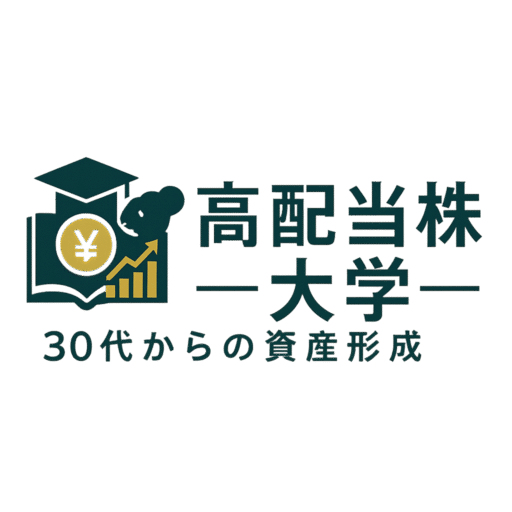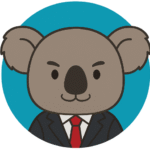株主優待は“楽しみながら学べる”高配当株初心者におすすめの手法
導入
株主優待は、高配当株投資を始めたばかりの方にもおすすめできる手法です。
数字の上でも合理的ですし、企業を「応援したい」と思える気持ちも育ちます。
そして、株主としての“楽しみ”が増える点も魅力です。
投資は続けることが大事ですが、そのモチベーションとして「優待が届く楽しみ」は想像以上に効果があります。
自社製品を扱う企業の優待は特におすすめ
私が特に良いと思っているのは、自社製品を株主優待として提供している企業です。
なぜなら、会社側が「買って外部から調達して渡す」よりも、自社で作った商品を原価で提供する方が合理的だからです。
投資家は“売値ベース”の価値を受け取り、企業は“原価ベース”で提供できる。
まさに双方にメリットのある仕組みです。
自社サービスを提供する優待の例
楽天
- 優待内容:通信回線(スマホの通話料割引)
- 特徴:日常的に使うサービスなので利用価値が高い
- 企業側メリット:回線1契約あたりの追加コスト(原価)はごく小さい
U-NEXT
- 優待内容:6か月分の動画配信サービス
- 特徴:動画視聴を楽しむ人には“売値ベース”で大きな価値
- 企業側メリット:アカウント追加の原価はほぼ固定費内で吸収可能
スマホ1回線や動画配信1アカウントを増やすコストはわずかでも、
利用者からすれば数千円〜1万円相当の価値を受け取れます。
このように、企業にとっても投資家にとっても合理的な仕組みになっています。
数字で見ても合理的:配当の一部として考える
株主優待は「現物でもらえる配当」と考えるとわかりやすいです。
たとえば年間5,000円分の優待を受け取るなら、それは**+0.5〜1%の配当増**に相当します。
現金配当と違って生活の中で“使って消費できる”のも魅力です。
数字を超える「満足度リターン」
優待の魅力は、数字で測れない満足度の高さにもあります。
現金配当と違い、「届く楽しみ」「使う喜び」があるのです。
私のお気に入り優待例
- ジェリービーンズ:靴の優待(倒産リスクあり、今はおすすめできませんが、もらった靴の価値で投資額は回収できたので満足)
- トリドール(丸亀製麺):家族で使える定番優待
- HUB(ハブ):ちょっとした贅沢感を味わえる飲食系
月に1回くらい何か優待が届くと、それだけで日常に小さな楽しみが増えます。
「投資を続けてよかった」と感じられる瞬間です。
リスクも理解しておく
もちろん、株主優待にも注意点はあります。
- 優待廃止のリスク:最近はコーポガバナンス改革の流れで廃止が増加
- 株価下落リスク:廃止が発表されると株価が大きく下がる傾向
- 確定日前後の値動き:優待目的の短期売買が多く、割高になることもある
特に、優待を目的にした投資は「優待がなくなった瞬間に魅力が消える」点に注意が必要です。
あくまで**配当を軸に、優待は“楽しみのボーナス”**と考えるのが現実的です。
まとめ
株主優待は、高配当株投資を始めたばかりの方にもおすすめできる“楽しみながら学べる投資手法”です。
特に自社製品を提供する企業の優待は、企業にも投資家にも合理的で、満足度も高い。
ただし、優待廃止や株価変動のリスクは常に意識しておきましょう。
「配当+優待=お金と心の両面で豊かにするリターン」
この視点を持つと、投資がもっと長く、楽しく続けられるようになります。
※本記事は特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。